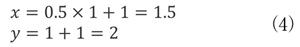流体解析の基礎講座
ソフトウェア・ハードウェアの急速な進歩に伴い、設計・開発を取り巻く環境は近年大きく変わりつつあります。2次元で描いていた図面は3次元で描くようになり、 CAE(Computer Aided Engineering) が活用される機会が多くなってきました。このような流れの中で、これまでは解析専任者のみが使用していた 熱流体解析 (Computational Fluid Dynamics: CFD)ソフトウェアを設計者などの解析専任者ではない人が使用するケースも増えています。この状況は技術者のスキルの1つとして熱流体解析が求められていることを表しているともいえます。ところが、これから熱流体解析を始めようとする人の中には、多忙な業務の合間に 流体力学 やCFDの分野に見られる難解な理論や専門用語を理解することが難しく、なかなか使いこなせるところまで到達できないという方もいらっしゃると思います。そこで、この連載では熱流体解析をこれから始める方、もしくは始めて間もない方を対象に、熱流体解析を行う上で基本となる内容についてご紹介していきたいと思います。
コンテンツの作成にあたっては難しい表現や式の記述をできるだけ避け、感覚で理解しやすいように努めました。本連載が皆さまの業務にとって有益な情報となりましたら幸いです。
-
1.1 熱流体が関わる現象,1.2 熱流体解析の利点と注意点
-
2.1 密度,2.2 粘性係数
-
2.3 比熱,2.4 熱伝導率
-
3.1.1 速度と速さ、流量,3.1.2 圧力
-
3.1.3 流線と流脈線、流跡線
-
3.2.1 圧縮性と非圧縮性
-
3.2.2 定常と非定常,3.2.3 ベルヌーイの定理
-
3.2.4 層流と乱流
-
4.1 温度と熱,4.2 浮力,4.3 自然対流と強制対流
-
4.4.1 熱伝導,4.4.2 対流熱伝達
-
4.4.3 輻射
-
5.1 基礎方程式と離散化
-
5.2 有限体積法
-
5.3 解析領域,5.4 空間の分割
-
5.5 境界条件,5.6 初期条件
-
5.7 マトリックス解法
-
5.8 時間の進行
-
5.9.1 レイノルズ平均モデル(RANS), 5.9.2 ラージエディシミュレーション(LES)
-
5.9.3 直接数値シミュレーション

著者プロフィール
上山 篤史 | 1983年9月 兵庫県生まれ
大阪大学大学院 工学研究科 機械工学専攻 博士後期課程修了
博士(工学)
学生時代は流体・構造連成問題に対する計算手法の研究に従事。入社後は、ソフトウェアクレイドル技術部コンサルティングエンジニアとして、既存ユーザーの技術サポートやセミナー、トレーニング業務などを担当。
最後までお読みいただきありがとうございます。ご意見、ご要望などございましたら、下記にご入力ください